『公共選択論』 高橋智彦(政経学部教授)、宮下量久(政経学部教授)共著
掲載日:2022年01月27日
『公共選択論』
本書「公共選択論」は経済学や政治学の基本知識を持った初学者が次に進むステップとして読むテキストです。政治経済分野の実際のトピックや最新の話題を提供し、実証分析も含めた公共選択理論の紹介、様々な制度の政治経済学的分析と制度の選択、政策課題の解決を扱っています。対象は「公共選択学会 学生の集い」(毎年12月開催)に参加するような2年生以上の学生を想定しています。
全16章からなり、本学の高橋智彦教授が第6章「中央銀行と金融政策」、宮下量久教授が第15章「政権選択」を執筆しています。
第6章「中央銀行と金融政策」では金利操作などの伝統的金融政策と量的緩和やマイナス金利などの非伝統的金融政策の各々について説明しています。また、フィンテックによって各種の暗号資産とよばれるデジタル通貨などが台頭し、対抗上中央銀行デジタル通貨(CBDC)を発行し、環境問題にも対応するなど政策手段が限られる中で役割が広がっていることなど、過去から現代の問題を網羅的に紹介しています。
第15章「政権選択」では、市民は何を基準に政権を選ぶべきかを議論しています。政治家は得票最大化のために各政策を決定すると考えた場合、選挙時期には好景気、積極財政になる傾向があるといわれています。このような政策形成過程が社会における公平性や効率性を著しく阻害していれば、政治体制や選挙制度、財政・金融制度、さらに憲法などを見直す必要があることを説明しています。
ー目次―
はじめに
第1部 公共選択論で考えよう
序章 公共選択論とは何か
第1章 財政赤字、財政の持続可能性の諸条件と財政破綻
第2章 インフラ整備と高級追う投資の公共選択
第3章 地方財政に見る公共選択
第4章 民営化・競争政策
第5章 少子高齢化と社会保障
第6章 中央銀行と金融政策
第2部 公共選択論と政策形成過程
第7章 公共選択論の基礎理論
第8章 投票行動
第9章 選挙制度
第10章 議会制度と権力の分立・融合
第11章 行政制度
第12章 実験経済学とナッジによる政策目標の実現
第3部 制度選択と制度改革の公共選択論
第13章 立憲的政治経済学
第14章 立憲的政府の形成と改変
第15章 政権選択
第16章 国際的合意形成:国際組織に関するものを中心に
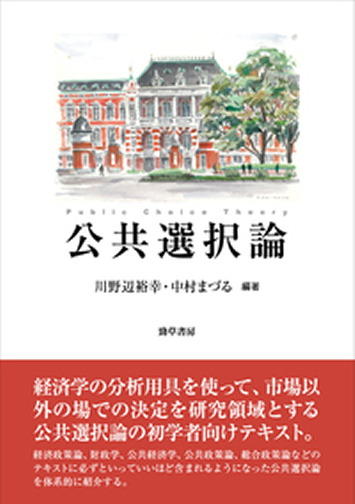
出版社
勁草書房
発行日
2022年1月
著者

高橋智彦(たかはし ともひこ)
拓殖大学政経学部教授
筑波大学経営・政策科学研究科博士後期課程修了 博士(経営学) 専攻 国際金融論、金融論
主要著書:「改正日銀法と中央銀行の独立性」『公共選択の研究』第34号、2000年、pp31-42.、「証券化―新たな使命とリスクの検証」(共著)金融財政事情研究会、川北英隆編著、桑木小恵子、渋谷陽一郎、高橋智彦著、2012年

宮下量久(みやした ともひさ)
拓殖大学政経学部教授
法政大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期課程修了、博士(経済学)、専攻:公共選択論、財政学
主要著書:『「平成の大合併」の政治経済学』(共著)勁草書房、2016年、「市町村における財政調整基金の積立要因に関する実証分析」(共著)『計画行政』第43巻第4号、2020年、pp.39-47.


