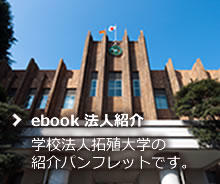言語文化研究所
概要
言語文化研究所は、言語文化についての学術活動を発展させることを目標とし、次の事業を行っています。
- 言語文化に関する調査研究
- 言語文化に関する刊行物の発行
- 言語文化に関する研究会、講演会、シンポジウム、公開講座等の開催
- 研究所において実施することが適当と認められる言語教育
- その他、研究所の目的を達成するために必要な事業
本究所の特徴のひとつとして、公開講座「外国語講座」を開講していることがあげられます。
本研究所の前身である日本語研修所(のち、語学研究所と改称され、現在、言語文化研究所)はインドネシア共和国賠償留学生に日本語を教えるという目的のために設立されて以来、言語(語学)についての教育・研究を行っています。
言語文化研究所長挨拶
狩野 紀子(外国語学部教授)
本研究所の歴史は、1961年に設立された「日本語研修所」に始まります。その後、三度の名称変更を経て、現在の「言語文化研究所」となりました。「日本語研修所」は、アジア協会から委託を受け、インドネシア共和国の賠償研修生に日本語を教えることを目的として設立されました。2年後の1963年には「語学研修所」と改称され、翌年の1964年には東京都の海外移住講座として、ブラジル語やスペイン語などの講義が始まりました。その後も研究と教育の対象となる言語が増え、1972年には「語学研究所」へと再び名称が変更されました。また、同年には研究所の機関誌として『語学研究』(現在の『拓殖大学 語学研究』)が創刊され、当時の総長である豊田悌助氏が「拓殖大学と語学研究」と題した前書きを寄せています。そして、1997年には学内の研究制度の整備に伴い、現在の「言語文化研究所」という名称になりました。
本研究所は長い歴史を持ちながらも、時代のニーズを積極的に取り入れ、新たな挑戦を続けてまいりました。2020年には、研究所に所属する教員は50名を超え、拓殖大学の5つの学部や大学院、さらには拓殖大学北海道短期大学の教員も含まれています。本研究所の活動は多岐にわたります。言語や文化に関する研究支援や出版助成のほか、シンポジウムや講演会の開催も行っています。また、「外国語講座」を開講し、本学の学生だけでなく一般の方々にも学びの場を提供しています。2025年現在、韓国語、タイ語、台湾語、中国語、ベトナム語の計5言語の講座を開講しています。
言語は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、文化を形づくる重要な役割を持っています。ソシュールの登場以降、このことがより明確になり、私たちの言葉が文化そのものを生み出していることが理解されるようになりました。また、言語は常に変化し続ける存在でもあります。この変化こそが、言語や文化の本質といえるでしょう。急速なグローバル化に伴い、言語や文化の新たな側面が生まれています。本研究所では、世界の国々や地域の言語や文化の違いを多様性として捉え、研究と教育活動を進めてまいります。今後とも、皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

出版物
紀要『拓殖大学 語学研究』
第137号以降は拓殖大学機関リポジトリに論文を掲載しております。
公開講座
文京アカデミア講座のお知らせ
文京アカデミア講座は、多様な分野について学ぶことのできる生涯学習講座です。文京区内在住・在勤・在学者を対象に、有料で開講しています。詳しくは文京アカデミーのホームページでご確認ください。
2022年5月14日(土)、28日(土)、6月11日(土)開催 13:30~15:00 [全3回]
- 講師:池田 朋洋 外国語学部助教
- 「文化人類学への誘い」
文化人類学のおもしろさは、自分たちの「当たり前」を問い直すところにあります。玄関では靴を脱ぐ、贈り物をもらったらお返しをするなど、私たちが「当たり前」と思っている身の回りの出来事について、様々な国の事例を見ていくことで見つめ直してみませんか?
| ①5/14 | 文化人類学とは? |
|---|---|
| ②5/28 | 人びとを結び付ける贈り物の文化 |
| ③6/11 | 世界の様々な結婚・家族・親族のあり方 |
| 定 員 | 30名 |
| 会 場 | 文京キャンパス |
| 講座形式 | 対面式講座 ※対面での実施が難しくなった場合、「Zoom」を使ったオンライン講座に切り替えます。 |
2021年度の開講実績
2021年12月4日(土)、11(土)、18日(土)開催 11:00~12:30 [全3回]
- 講師:佐野 正俊 言語文化研究所所長・外国語学部教授
- 講座:「宮沢賢治入門」
宮沢賢治の生涯をたどりながら、代表的な作品の一部を読みます。賢治の作品は、その「わからなさ」が魅力であるといえます。感性を働かせて、彼の作品の魅力を味わいましょう。
| ①12/4 | 『注文の多い料理店』を中心にして |
|---|---|
| ②12/11 | 『春と修羅』を中心にして |
| ③12/18 | 『銀河鉄道の夜』を中心にして |
| 定 員 | 30名 |
| 会 場 | 文京キャンパスC館 C401教室 |
| 講座形式 | 対面式講座 ※対面での実施が難しくなった場合、「Zoom」を使ったオンライン講座に切り替えます。 |
ご質問などがございましたら、kenkyu@ofc.takushoku-u.ac.jp宛に電子メールでご連絡いただけますようお願い申しあげます。