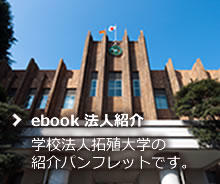海外事情研究所
概要
海外事情研究所は、本学の建学の理念に則り、広く内外の関係と呼応して、海外事情及び国際問題を調査研究し、もって学術の進歩と日本の国益、地域の共栄並びに世界の平和と発展に寄与することを目的とし、次の事業を行っています。
- 海外事情と国際問題の調査研究
- 『海外事情』の発行
- 調査研究に基づく提言、報告及び文献等の発表ないし刊行
- 内外関係機関との交流、協力及び共同研究の受・委託
- 海外事情及び国際問題に関し、主として拓殖大学、拓殖大学北海道短期大学の学生に対する教育指導
- 研究会、講演会、講習会、シンポジウム及び公開講座等の開催
- その他、研究所の目的を達成するために必要な事業
『海外事情』を隔月発行し、公開講座「国際講座」を開講するなど積極的に社会に広く還元する活動をしています。
海外事情研究所長挨拶
佐藤 丙午(国際学部教授)
拓殖大学海外事情研究所の所長の佐藤丙午です。
海外事情研究所は、拓殖大学の歴史の中でも独特な位置付けにあります。その長い伝統と、先達の業績を思う時、身の引き締まる思いで所長の職を引き継ぎ、業務に取り組んできました。 海外事情研究所は、1955年(昭和30 年)、本学の「建学の精神に則り広く内外の関係と呼応して、海外事情及び国際問題を調査研究し、もって学術の進歩と日本の国益、地域の共栄並びに世界の平和と発展に寄与すること」を目的として設立されました。
そして、今日に至るまで、海外事情研究所は国際情勢の分析を通じ、国内外の研究者と共に、日本の国際的な発展に貢献することを目指してきました。そして、海外事情研究所の調査分析の焦点は、地域研究を基本としながら、時代の要請と共に変化してきました。日本人の海外雄飛が必要な時代は、その人材の活動に貢献できるような調査分析を進めてきましたし、国際援助や平和構築が日本の国際政策の中心に置かれた時代は、それらを重視してきました。この役割は、今日でも変化していません。そして、海外事情研究所は時代の変化の中で、日本の外交・安全保障政策の課題を発見し、それを解決するための方法を模索し、提案してきました。
現在国際社会は、大きな変化に直面していると思います。国連の意思決定は停滞し、国際社会では様々な分断が顕在化しています。ウクライナや中東における状況を見るまでもなく、軍事的な緊張は高まり、核兵器を含めた軍事問題に対して、慎重にかつ大胆に対応する必要が生まれています。つまり、国際秩序の変動が進展していると判断できる要素が増えているのです。
日本の外交安全保障政策は、このような変動に対応していく必要があります。政策には正解はありません。必要なのは、時代における適切な政策を模索し、その方法を考案していくことなのだと思います。過去の成功体験や、諸外国での成功例を模倣するのは簡単ですが、今日の国際社会では、それが許されない状況が生まれています。
本研究所は、こうした混沌とする国際情勢の分析と地球規模の諸課題の解決に向けて、より一層充実した調査・研究活動に取り組み、その成果を積極的に国内外へ提言・発信して参ります。

海外事情研究所オリジナルサイト
華僑研究センター
※華僑研究センターは、平成26年3月末日をもって廃止となりました。
出版物
※ 『海外事情』のバックナンバーは研究支援課までお問い合わせください。
『海外事情』 (学内閲覧のみ)
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
『海外事情』 2025年 目次
『海外事情』 2024年 目次
『海外事情』 2023年 目次
『海外事情』 2022年 目次
『海外事情』 2021年 目次
『海外事情』 2020年 目次
『海外事情』 2019年 目次
『海外事情』 2018年 目次
『海外事情』 2017年度 目次
『海外事情』 2016年度 目次
『海外事情』 2015年度 目次
公開講座
ご質問などがございましたら、kaiken@ofc.takushoku-u.ac.jp宛に電子メールでご連絡いただけますようお願い申しあげます。